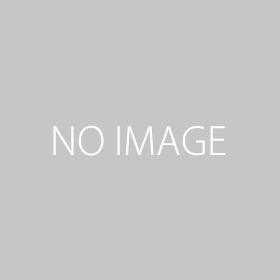企業側・従業員側それぞれにさまざまなメリットがある社員食堂は、中小企業におすすめの食に関する福利厚生の一環。
福利厚生として導入することで、健康経営の実現はもちろん、節税対策にもつながります。
ただ、スペースや運営方法などの問題から、導入したくても迷っている中小企業は少なくありません。
この記事では、中小企業が福利厚生として社員食堂を導入する理由や導入の流れ、税制優遇などについて、詳しく解説します。
社員食堂が従業員に与えるメリットについても説明するので、ぜひ参考にしてください。
目次
中小企業が福利厚生として社員食堂を導入する理由とは?
中小企業こそぜひ導入をしたいのが、福利厚生としての社員食堂です。
最初に、中小企業が福利厚生として社員食堂を導入する主な理由について説明します。
従業員の健康維持と生産性向上につながる
一番の理由としてあげられるのは、従業員の健康維持や健康促進です。
社員食堂では、栄養士が考えた栄養バランスを考慮した食事を提供しています。
健康的な食事を提供することで、自然と健康意識も高められるでしょう。
心身共に健康な状態であれば仕事に対するやる気も高められ、生産性の向上につながります。
人材採用・定着率向上に効果的
社員食堂を導入しているところは、福利厚生が充実している会社であり、企業のイメージアップにもなります。
福利厚生は、会社を選ぶ際に重要視するポイントでもあり、人材採用には非常に効果的です。
また、社内で手軽に食事が摂れる環境を提供するのは、モチベーションの向上にもつながり離職率の低下も期待できるでしょう。
福利厚生の導入は、外部への大きなアピールポイントの1つです。
ランチ難民の解消と職場の満足度向上
郊外にあることも多い中小企業は、都市部に集まっている大企業とは違い、職場周辺に飲食店が充実していません。
飲食店があっても人が集中するため、昼食を摂りそびれてしまう「ランチ難民」がうまれてしまいます。
社員食堂があれば飲食店やコンビニなどを探す必要がなく、社内でゆっくりと食事を摂りながら過ごせます。
貴重なランチタイムを有意義に過ごすことができ、職場の満足度アップにつながるでしょう。
福利厚生として社員食堂を導入する流れ
自社に合った社員食堂を導入するには、流れをしっかりと理解しておくことも大切です。
福利厚生として社員食堂を導入する際の流れを、事前に理解しておくとスムーズに進められます。
導入前に行うべき現状分析とヒアリング
最初に行うべきことは、従業員へのヒアリングです。
実際に利用する従業員のニーズを聞くためにアンケート調査などを実施すると、求めているものが正しく把握できるでしょう。
社員食堂に求める項目やメニュー、利用頻度、価格帯など、希望を明確にすることが大切です。
現状の分析とヒアリングをもとに、従業員に満足してもらえる社員食堂作りを検討していきましょう。
運営方式・委託形態の検討と選定
次に、社員食堂として利用するスペースなども考慮したうえで、運営方式や委託形態を検討します。
社員食堂の運営方式には、直営・準直営・外部委託の3つがあり、外部委託であれば、運営に関するノウハウがなくても問題ありません。
直営や準直営とは違い、人材雇用にかかる費用や手間をかけずに、自社に合った満足度の高い社員食堂の導入が実現できます。
委託業者の選定と見積もり取得
運営方式や委託形態を決定したら、委託する業者を選定します。
公式サイトでサービス内容や特徴などを確認し、実績が豊富な業者を選びましょう。
業者によっては、運営している社員食堂の見学会や試食会を行っているところもあるので、利用するのもおすすめです。
委託業者を選定したら、見積もりを出してもらいましょう。
契約・設備準備
サービス内容や見積もり、プランなど、すべてにおいて納得できたら契約を結びます。
委託会社では、豊富な実績をもとに、それぞれの会社に合わせたスタイルの社員食堂の導入を実現してくれます。
広いスペースの確保が難しい中小企業でも、レイアウトの工夫や設備の選択などで、ゆったりと過ごせる環境作りは可能です。
委託会社とコミュニケーションを取りながら、準備を進めていきましょう。
社員食堂を福利厚生として導入した場合の税制優遇とは?
社員食堂は、福利厚生として導入することで税制上の優遇が受けられます。
どのような優遇が受けられるのか、福利厚生として導入する条件と合わせて見ていきましょう。
一定条件を満たせば会社負担分が非課税に
昼食代は、会社が全額負担すると給与として扱われるため、福利厚生にはなりません。
福利厚生として導入するには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。
・役員や従業員が50%以上の費用を負担している
・会社の負担額が1人あたり月3,500円(税別)以下
例えば、月に5,000円の食材費がかかる場合、従業員が2,500以上を負担し、会社が2,500円未満を負担するのであれば、福利厚生として計上が可能です。
条件を満たしていれば、税務上の優遇措置が受けられます。
法人税上の損金処理が可能
福利厚生として条件を満たしていれば経費として計上されて損金扱いとなり、法人税の節税につながります。
社員食堂の運営費を経費として計上すれば、課税対象となる所得を減らすことができ、法人税の負担が軽減できるのです。
福利厚生としての社員食堂の導入は、会社にとって節税というメリットをもたらしてくれます。
福利厚生としての社員食堂が従業員にもたらすメリット
節税対策など、企業側にとってメリットがある福利厚生としての社員食堂は、従業員にもメリットがあり人気です。
福利厚生としての社員食堂が従業員にもたらす、主なメリットについて説明します。
健康意識の向上と生活習慣の改善
毎日忙しく働いていると、ついインスタント食品やコンビニ食で簡単に済ませてしまう場合が少なくありません。
しかし、社員食堂があれば、栄養士が考えた栄養バランスが整ったメニューが食べられるので、自然と健康意識が高まります。
生活習慣も改善でき、健康維持や健康増進につながるところが大きなメリットです。
業務効率の向上と集中力アップ
栄養バランスが整った食事は、やる気や集中力とも大きく関係しています。
また、ストレスに負けない強い精神力作りも目指せるでしょう。
心身共に健康な状態であれば仕事に対するモチベーションも上がり、業務効率も向上します。
コミュニケーション活性化による社内の一体感
ランチタイムになれば、従業員が自然と社員食堂に集まり、さまざまな部署の人と交流できます。
仕事の話はもちろん、プライベートの話題を話す機会もあり、コミュニケーションの活性化につながるところもメリットです。
従業員同士の関係性がより深められて一体感ができ、職場の雰囲気も良くなるでしょう。
まとめ
福利厚生としての社員食堂の導入は、従業員にもたらすさまざまなメリットがあり、中小企業におすすめの施策です。
多くの会社が注目している健康経営の実現はもちろん、税制優遇が受けられるので節税対策にもつながります。
社員食堂の導入を検討している中小企業は、まずは委託業者に相談してみるのがおすすめです。
社員食堂を導入する流れを理解したうえで委託業者に依頼して、自社に合った満足できる社員食堂の導入を実現させましょう。

1973年 京都府城陽市で創業
社員食堂の運営を通じて顧客の人財確保と福利厚生制度の充実に貢献。
「食文化の向上」を企業理念とし、給食を価値ある食事にしていき、深い信頼と絆でさらに長くお付き合い頂ける企業を目指す。
◆事業内容◆
事業所や厚生施設、官公庁の庁舎、研修所における社員食堂及び、大学や高等学校専門学校 の学生食堂を運営。中小企業(30~40人の小規模事業所等)の 社員食堂事業を新事業として展開。レトルト事業開始。
主な得意先:HILLTOP株式会社(京都府)、株式会社神戸製鋼所、京セラ株式会社、京都産業大学、学校法人履正社、キユーピー醸造株式会社、キリンビール株式会社、他多数
◆実績・メディア掲載◆
ダイアモンドオンライン HILLTOP株式会社(京都府)様 取材
大阪中小企業投資育成株式会社 投資先企業
近畿経済産業局 関西企業フロントラインNEXT 新事業展開成功事例として取り上げられる