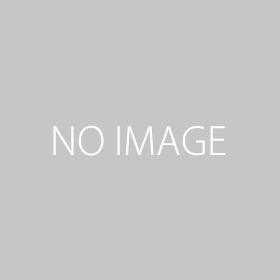「福利厚生」とは、従業員やその家族の健康増進や生活の向上を目的とした、給与などの基本的な労働対価とは別に提供する報酬のこと。
飲食に関する福利厚生の一貫として、社員食堂を導入する企業も増えています。
ただ、福利厚生として認められる飲食の範囲というのは決められているため、すべてが対象というわけではありません。
節税の観点からもメリットがある社員食堂を、福利厚生の一貫として上手く取り入れるためにも、飲食の範囲をしっかりと理解しておきましょう。
そこでこの記事では、福利厚生で認められる飲食の範囲や社員食堂を導入するメリット、さらに、社員食堂を導入する方法について詳しくご説明いたします。
目次
福利厚生でみとめられる飲食の範囲は?
従業員の飲食代の補助は、福利厚生として認められていますが、すべてが対象ではありません。
まずは、飲食の範囲をしっかりと理解しておきましょう。
上限内で計上できる飲食代はOK
福利厚生として計上できる飲食代は、上限内であれば非課税となります。
勤務中の飲食代の補助について、福利厚生として認められる条件は以下の2点であり、その2つの要件を満たしておかなくてはいけません。
・食事代の50%以上を従業員が負担していること
・企業が負担する飲食にかかる費用が、1人当たり月額3,500円以内であること
例えば、1人当たりの月の飲食代が7,000円で、3,000円を企業が負担しているとします。
上記の場合、従業員は半分以上の4,000円を負担し、企業が負担する費用も3,500円以下のため、福利厚生として処理されます。
残業や日直者に支給する夕食・夜食はOK
残業や宿直、日直者に支給する夕食や夜食については、福利厚生として認められているため計上ができます。
ただ、現物での支給はNG、そして、必ず残業または宿日直の時間帯であることが条件です。
また、上限金額の決まりはありませんが、飲食代が高すぎる場合は認められないケースもあるため注意をしましょう。
接待や勤務後の飲食代はNG
取引先をもてなすための接待や、勤務時間が終わった後の飲食代は、福利厚生として認められません。
接待での飲食代は、福利厚生ではなく交際費です。
勤務後の飲食代についても、業務時間とは全く関係ないため、福利厚生の対象にはなりません。
福利厚生として食事補助を支給する主な方法とは
福利厚生の中でも「食事補助」は、従業員の満足度や健康管理に直結する重要な制度です。
社員食堂の他にも、多様な方法で食事補助を導入することが可能です。ここでは、中小企業でも実施しやすく、コストや運用負担を抑えながら効果的に導入できる「食事補助の主な支給方法」をご紹介します。自社に合った方法を選ぶ参考にしてください。
社員食堂の設置・運営(自社運営・外部委託)
もっとも一般的な食事補助の方法で、企業内に社員食堂を設けて、従業員が低価格または無料で食事を取れるようにする制度です。
社員食堂は、従業員の健康管理や業務効率の向上、社内コミュニケーションの促進にもつながることから、導入企業が増加しています。自社での運営が難しい場合は、外部の委託会社に任せる形での運用も可能です。
食事手当の支給(ランチ手当・食費補助)
給与とは別に、毎月一定額の食費を手当として支給する方法です。手当額は企業ごとに自由に設定でき、柔軟な制度設計が可能です。特に社員食堂が設置できない企業でも導入しやすく、従業員が自分の好きな店で食事を選べるという自由度の高さが特徴です。ただし、課税・非課税の条件には注意が必要です。
食事券(クーポン・チケット)制度の導入
ジェフグルメカードやチケットレストランなど、特定の飲食店やコンビニで利用できる食事券を従業員に配布する制度です。
企業側は利用可能店舗の指定ができ、実質的に“食事に使うことを前提とした補助”が可能になります。
条件を満たせば非課税扱いにできるメリットもあり、実用性と税制優遇の両面で活用されています。
ケータリング・デリバリー形式の導入
外部の弁当業者や飲食サービス会社と契約し、従業員にランチを社内で提供する方式です。社員食堂ほど大掛かりな設備は不要で、日替わりメニューや栄養バランスに配慮した食事を提供できるのが魅力です。
企業が一部または全額を補助することで、従業員の食事費負担を軽減することが可能です。
オフィスコンビニ・社内冷蔵庫の設置
オフィス内に無人販売型の冷蔵庫や軽食販売機を設置する方法です。「オフィスおかん」や「オフィスグリコ」などが代表的なサービスで、簡単に軽食や惣菜が購入でき、企業が一部補助することで食事補助とすることが可能です。
スペースが少なくても導入でき、24時間いつでも利用できる利便性も魅力です。
非課税で食事補助を支給するための主な条件(所得税法上)
企業が従業員に食費の補助をする場合、それが所得税の課税対象になるかどうかが条件によって変わります。
以下に、食事補助が「非課税」になるための代表的な条件をわかりやすく解説します。
社員食堂のように食事を現物で提供していること
企業が従業員に食堂や弁当などの「現物」を提供する場合、非課税となるケースがあります。
ただし、その自己負担額が1食当たり「半額以上」または「1食あたり330円以上」であることが条件です(※どちらかを満たせばOK)。
例えば社員食堂で1食600円の食事を提供する場合、従業員が330円以上を自己負担すれば、会社が補助した残りの270円は非課税になります。
現金で支給する「食事手当」は原則課税対象
現金で「ランチ代」として手当を支給する場合、原則として給与とみなされて課税対象になります。
つまり、食事に使う目的であっても、現金で支給すれば所得税がかかるのです。
| 補助方法 | 非課税になる? | 条件 |
|---|---|---|
| 社員食堂・仕出し弁当(現物) | ✅ 非課税 | 従業員が半額以上 or 1食330円以上自己負担 |
| 食事クーポン(一定の条件を満たす場合) | ✅ 非課税 | 使用目的が限定されていることなど |
| 現金による「食事手当」 | ❌ 課税 | 給与と同様に扱われる |
福利厚生に社員食堂を導入するメリット
福利厚生の一貫としての社員食堂の導入は、企業にとってさまざまなメリットがあります。
社員食堂を導入するメリットを、詳しく見ていきましょう。
飲食の負担が減り従業員の経済的支援になる
従業員にとって、経済的に大きな負担となるのが、毎日の飲食代です。
安い値段で食事ができる社員食堂があれば、飲食の負担が減るため経済的な支援ができます。
また、社員食堂で出される食事は、栄養バランスが整っているため、従業員の健康維持にもつながるでしょう。
その結果、ベストな状態で働けるため生産性が低下する心配もなく、体調不良などによる離職も防げます。
企業の節税対策になる
企業が負担した社員食堂の運営費は、課税されない要件を満たしていれば福利厚生としての計上が可能。
企業の節税対策になる点も、大きなメリットの一つです。
福利厚生として認められる以下の2点の条件を、しっかりと理解しておきましょう。
・食事代の50%以上を従業員が負担していること
・企業が負担する飲食代の費用が、1人当たり月額3,500円以内であること
福利厚生に社員食堂を導入する方法は?
福利厚生として社員食堂を導入するためには、さまざまな準備が必要となることも覚えておきましょう。
企業のアピールポイントにもなる社員食堂を導入する方法を、詳しくご説明します。
従業員のニーズを調べる
最初に、どのくらいの利用者が見込めるのか、従業員のニーズを調べましょう。
せっかく社員食堂を導入しても、従業員に利用してもらえなければ、負担ばかりが大きくなってしまいます。
例えば、社員食堂にどのくらいの関心があるか、どのような社員食堂なら利用してみたいかなど、事前にアンケートを取ってみるのもおすすめです。
運営・提供方式を決める
社員食堂の運営・提供方式には、多くわけて3つの種類があります。
・自社で設立して自社だけで運営する「直営方式」
・運営会社を設立して社員食堂の運営を任せる「純直営方式」
・外部の専門業者に任せる「外部委託方式」
「外部委託方式」であれば、委託する費用はかかるものの、スタッフの採用から運営まで専門業者に全てを任せられます。
スムーズかつ安心して導入ができる、という点も大きなメリットです。
コストを計算する
社員食堂を運営するためには、さまざまな費用が発生します。
初期費用(厨房設備・委託管理費・改装費用など)、運営費用(水道光熱費・人件費・食費など)を含めたコストを計算するのも重要です。
委託業者や工事業者などに見積りを取った上で、問題なく運営ができるか慎重に検討をしましょう。

メニューを決める
多くの従業員に利用をしてもらうためにも、メニューを決めるのも大切な準備事項の一つです。
メニューが少ないと、従業員も飽きてしまい、利用率の低下につながってしまうかもしれません。
外部委託であれば、栄養バランスが良くて健康に良いメニュー、かつ、毎日通っても飽きないような、豊富なメニューが用意されています。
季節ごとの行事を盛り込んだメニューを取り入れるなど、魅力のある社員食堂が導入できるでしょう。
まとめ
福利厚生で認められる飲食は、上限の範囲内の飲食代でなければ計上ができません。
・食事代の50%以上を従業員が負担していること
・企業が負担する飲食代の費用が、1人当たり月額3,500円以内であること
福利厚生で認められる、以上の2点の要件をしっかりと覚えておきましょう。
福利厚生の一貫として、節税対策にもなる社員食堂を導入するのがおすすめです。
スムーズに導入ができる外部委託を利用して、従業員の満足度アップにもつなげましょう。

1973年 京都府城陽市で創業
社員食堂の運営を通じて顧客の人財確保と福利厚生制度の充実に貢献。
「食文化の向上」を企業理念とし、給食を価値ある食事にしていき、深い信頼と絆でさらに長くお付き合い頂ける企業を目指す。
◆事業内容◆
事業所や厚生施設、官公庁の庁舎、研修所における社員食堂及び、大学や高等学校専門学校 の学生食堂を運営。中小企業(30~40人の小規模事業所等)の 社員食堂事業を新事業として展開。レトルト事業開始。
主な得意先:HILLTOP株式会社(京都府)、株式会社神戸製鋼所、京セラ株式会社、京都産業大学、学校法人履正社、キユーピー醸造株式会社、キリンビール株式会社、他多数
◆実績・メディア掲載◆
ダイアモンドオンライン HILLTOP株式会社(京都府)様 取材
大阪中小企業投資育成株式会社 投資先企業
近畿経済産業局 関西企業フロントラインNEXT 新事業展開成功事例として取り上げられる